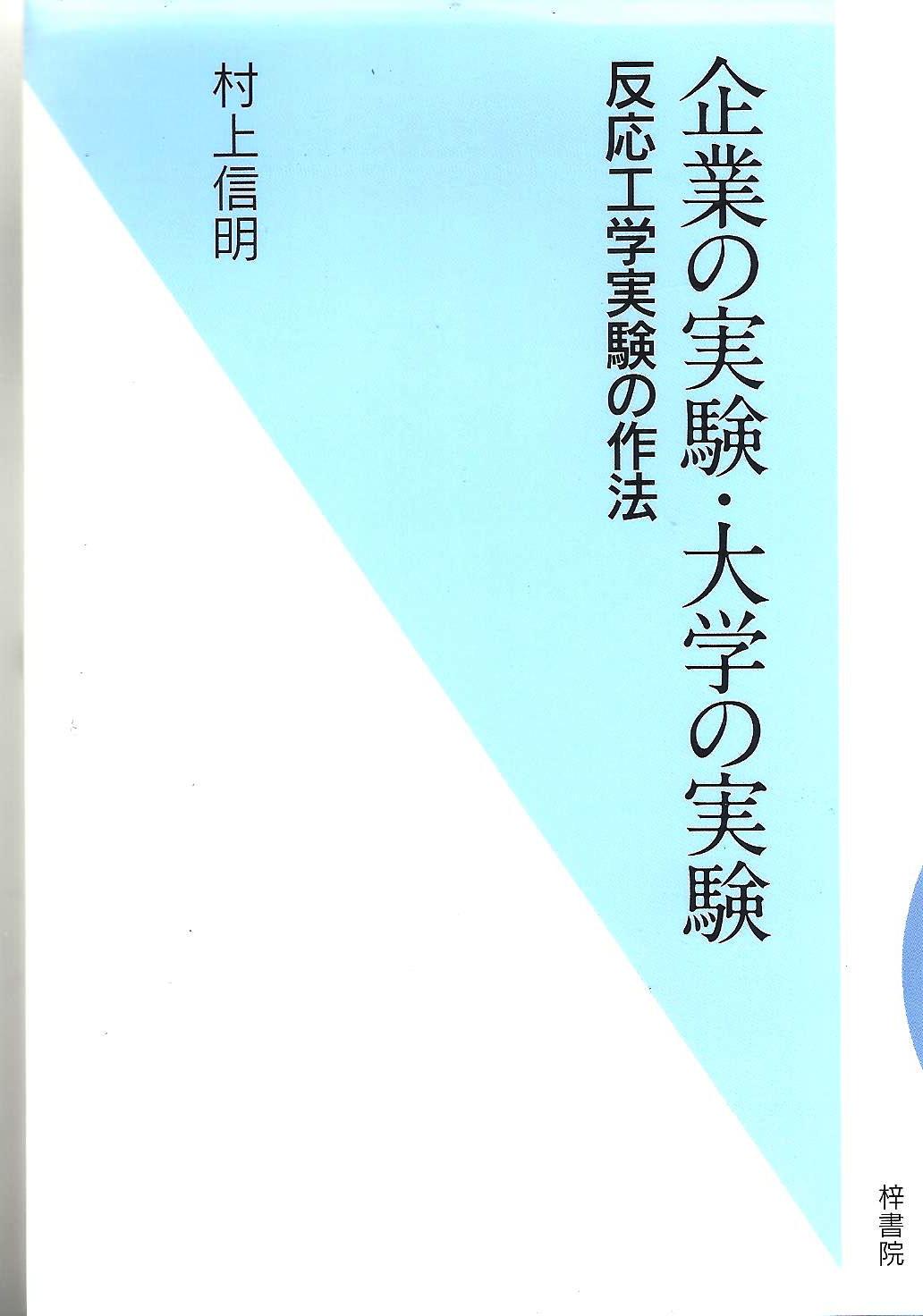学会論文と特許の効用
研究開発に関与した技術内容が、実際に工業的に利用される、これが我々の実験、研究の最終目標ではあるが、学会誌論文、特許、或いは学会での口頭発表は実験研究の当面の目的成果物の一つである。
学問・研究の世界と実業界は、最近は以前とはかなり違って、分かち難い部分も多くなってはいるが、それにしても一応は、学論文発表と特許出願は別物であり、研究者も別のものとして使い分けている。
一般に大学と企業では論文と特許の評価は異なっており、従って扱いもかなり違う。勿論大学は論文に重点があり、最近でこそ特許などを含む知的財産の利活用にも力をいれて、弁理士を講師とした授業などもされるようになったが、大学研究者の生命線である学術論文と比べてその評価は低い。また論文は自由にだせるが、特許を特許庁に出願するには、権利の帰属や費用の問題もあって、学内審査などの手続きが必要である。一方、企業ではその企業また技術者個人の活動状況の指標ともなる特許の出願は、推奨というより、業務の一環として半ば強制されることも特に研究職では多い。逆に、論文を出すのは特別な場合で、通常は不利益の有無についての実質的なチェックを含む承認が必要である。
特許は学術論文と比較して、文献としての価値が一般には低く見られている。特許は当該技術の権利化が主要目的であり、その範囲でしか技術内容は開示しないことが原則である。従って、なるべく少量の情報を出して、広い範囲の権利化を狙うための記述となり、また、それも最後は発明者自身ではなく多くは弁理士によっているから、当然ではある。
学術論文と特許については、以上のような一般的状況はあるが、最近では、世界的な飛び切りの科学賞の判断にも出願特許が使われ、その選定理由中にも明記されるようになった。特許の出願は実用的な意味だけからではなく、研究の優先性の確保という意味でも極めて重要と認識すべきであろう。ここで特許出願の実際的なテクニックの話をしても仕方がないが、まずは、若い頃から特許に慣れておく、また具体的な事件に関与することによって力もつくから、そのような機会には、人任せにせず積極的に関わるなど、自らの置かれた立場を勘案して対処することが望ましい。
いずれにせよ論文、特許とも、
九仞
の功
一簣
に
虧
く*は、誠に勿体ないことであり、文章表現まで含め深慮遠謀あるべきで、抜かりがあってはならない。レポートや論文のつくり方は学生の間は先生が程度の差こそあれ指導してくれるが、企業に行けばそうはいかない。昔は手書きで、上司に出した報告原稿が添削と評語で真っ赤になって戻ってきた、というのはよく聞いた話である。本当は、添削するより最初からその人が書いた方が早いが、それでは勉強にならないということであったろう。直される方も今のパソコンではないから、数か所でも大変で、清書しては添削・書き直しの繰り返しではあるが、その中で会得するものがあったに違いない。余裕のある古き良き時代といえる。今は、特別な場合は別にして、フォントも同じ没個性のワードの小さな文字であり、また上司も昔と違ってゆとりがないから細かな修正などしない、文章がいたらなくともただそう評価されるだけのことである。
今はパソコンが、文章中のおかしな用語や用法などお節介にも指摘してくれるから、近い将来、適当に原稿を入れてクリックすれば、誤字脱字、またラボアゼ、ラヴォアジェのような表現のゆらぎの類は勿論、もとの文章がどうあろうと、和文英文へだてなく、雲が行き水が流れるような完璧な文章の論文に仕立ててくれるかもしれない。それを期待する気持ちもないではないが、ただ、和文にしてもJIS第一水準だけで三千近くある漢字、それに仮名、学術用語まで含むとその処理は容易ではないだろうし、第一味気なくもある。
アンモニア合成法の発明で著名なフリッツ・ハーバーは、「彼の論文は、一年かかって得た結果を、さらに一年かけて文章を練りに練ってから完成したといわれるほど完璧だった」11)そうである。勿論後半の一年には文章のみでなく、実験内容のチェックや再試験なども含まれていただろう。成果の優先性が何より重要視される現在では、なかなか実行は難しいし、これまた状況によるとしか言えないが、報告、論文、特許をまとめるに当たってはそれなりの心構えと修練が必要ということである。
特許経験の一端
特許については、少なくはない数の発明者としての出願がある。というより多くの企業技術者と同様、公開した技術文書の大半は特許明細書であるから(多くは共同発明であるが、すべてを集めれば二、三千頁にはなるだろう)、いろいろの思い出がある。技術上の考案を特許として出願し、それにいろいろな形でかかわることは、特許法などの関連法と、技術とのせめぎあいという、日常の実験・研究業務とはかなり異質の面に参画することであるから、後々までも記憶に鮮やかである。技術者をみていると、特許については、興味を強くもつ人と無関心な人と、かなり明確に分かれるように思われる。自身は数十件以上の発明をしているに拘わらず、あとは特許担当任せで、それで何ごともなく技術者としての一生を終る人も多い。ただ、若い頃から興味を持ってやっていれば、年とともに知識・経験とも蓄積されてくる。もっとも中途半端な知識で、昔の制度との混同や、思い込みの類が多くはなる。
さて、会社生活も終わりの頃、これは自身の発明ではないが、ある事業部門の人から、窒素酸化物(NOx)の処理装置の問題で、二十年前の学位論文を訴訟の証拠資料として使わせて欲しいという依頼があった。業務上、お世話になっている人であり、断る理由もなく承諾したが、ただ、話を聞いてみると、こちらの主張にやや無理があるのでは、という内容であった。具体的な技術云々というより、特許法の条文解釈の問題として訴えを提起したもので、それで代理人も勝てる可能性があると言っているらしい。会社生活の最も多忙な時期だったこともあり、学位論文を裁判にどう使うのか聞きもせず、そのままにしておいた。
行政処分である特許庁審判官の審決に対する不服申し立ては、今は知的財産高等裁判所となっているが、当時は東京高裁の専轄であった。あとからその人に聞くと、判決の日は、報道陣も含め傍聴希望者で大混雑し大変だったとのこと。勿論、この特許の裁判傍聴のためではなく(こんな裁判は少数の関係者以外だれも傍聴しないだろう)、丁度その日は、例の重大事件である有機リン系猛毒薬物*
撒布
の控訴審の公判日だったためで、当方の裁判は予想通り敗訴であった。
特許の先願争い
前項のような例は一般の技術者が滅多に遭遇するようなものではない。言うまでもなく最も機会が多く、かつ重要なものは、特許権取得に関わるものである。
40年ほど前、ある国内企業A社と、特許権を争ったことがある。複雑な事情で、日本ではA社が先願、米国では当方の属する企業が先願となったものである。日本では二週間ほどの差であり、殆ど同じ内容であった。人も技術者も同じような時期に同じようなことを考えるものである。本当に不思議なことも時にあるが、多くはそれなりの理由がある。この場合は、一年ほど前に関連のユニークな特許が公開され、それに注目した研究者がある程度いて、かれらがアイデアをだし、実験を計画し、その費用を捻出し、薬品や器材を購入し整え、実際に実験を行い、さらにその結果を整理して、特許の形で執筆、社内手続きなどを経て出願したとすると、丁度その時期になったのである。明細書の原稿を書いた技術者は、勝手なもので、一日でも早く特許庁に提出して欲しいと思うものだが、担当部署での手続きもあり、なかなか思うようにはいかない。しかし、不思議なもので、日時がたつにつれ、興奮も収まってそれほど急いで出す程のものでもなかったと思えてくる。ただ、この場合はそれとは異なり、追加の実験や、次のステップの準備をしながら時に胸騒ぎのようなものがあった。
さて、日本では明らかにA社の出願が早いから仕方がない。問題は米国特許である。米国はその当時は、例外的な先発明主義国で、出願の先後によらず先に発明した方に権利が与えられる。状況としては後願のA社が、先発明の証拠を提示する必要があった。そこで出されてきたのがA社の研究所での実験日誌である。見ると、きちんとしたノートに、一日毎の試験内容、データが記され、職制の確認印が押されている。前述のいわゆる実験ノートであり、それ迄このようなものを見たことがなかったから、その企業に敬意を覚えたのを記憶している。ただ、やはりこちらには先願の強みがある。また双方の発明の時期を確定するのは容易ではない。米国特許庁に対して双方いろいろと言い分を出し合っていたが、ある段階で、社内からこの種争いは弁理士のドル箱である、日本企業同士の争いで、米国の弁理士を利してどうするのか、という声があがり、結局は和解することとなった。この特許の技術は残念ながら、本格的実用には至らなかった。ただ内容は後日、実験結果に解析を加え先方の特許出願をも引用させてもらって、いろいろな意味で記憶に残る論文にはなった。企業では簡単に論文を発表させてはくれない。不本意ではあるが、実用化に至らなかったからこそ、早めに拘束少なく学会誌に発表できたのである。
いずれにせよ、研究開発にあたってはライバルも常に同じようなことを考え、同じように計画し実験しているとの前提で、特許は可能な限り早期に出願するのが大原則である。
「企業の実験・大学の実験 反応工学実験の作法」(2022年8月刊、梓書院)
https://onl.bz/YeZ3SC (アマゾン)